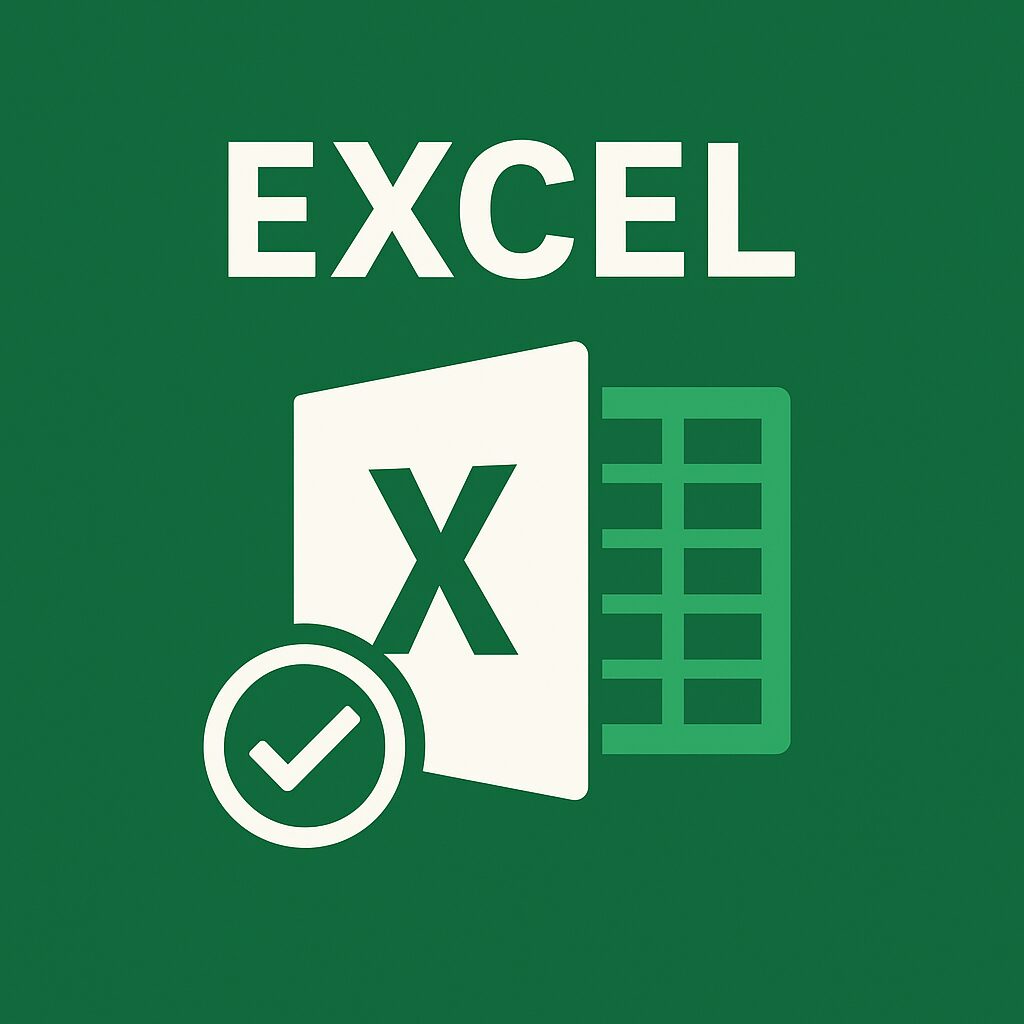Excel– category –
-

Excel:罫線が印刷されない/画面では見えるのに出ない時の原因と対策
Excelでは画面上では罫線が表示されているのに、印刷すると消えてしまうというトラブルが意外と多く発生します。特に資料提出や帳票印刷の直前に起きると焦りますよね。 この記事では、 なぜ「画面では見えるのに印刷されない」のか よくある原因パターン ... -

Excel スクロールバーが動かない | 画面スクロールが固定される問題の直し方
Excelを使っていると、「スクロールバーが動かない」「画面が上下左右に動かなくなった」といった症状に突然遭遇することがあります。 マウスやキーボードが壊れたわけでもなく、Excel自体もフリーズしていないのに操作できない──この記事では、Excelの画... -

Excel:文字が表示されない/#### 表示になる時の原因と対策
Excelを使っていると、 セルに入力した文字が表示されない 数値の代わりに「####」と表示される といった現象に遭遇することがあります。一見バグのように見えますが、ほとんどはExcelの仕様や表示設定が原因です。 本記事では、文字が表示されない・「###... -

Excel オートフィルター 効かない / 抽出できない理由と解決策
Excelでオートフィルターを設定しているのに抽出されない・一部の行がフィルタ対象にならないといったトラブルは意外と多いです。本記事では、フィルターが正常に動作しない原因と、それぞれの解決方法をまとめました。 ◆ この記事の対象者 フィルターを設... -

Excel 再計算されない 原因と対処法|値が更新されないときのチェックリスト
Excelを使用していると、数式を入力しているにも関わらず「値が更新されない」「参照元を変えても計算結果が変わらない」といった現象が起きることがあります。これは、Excelの設定や数式の状態に原因があることが多く、適切に確認すれば解決できます。 本... -

Excel 日付 勝手に変換される 問題を止める方法|例:2024-01 → 2024年1月
Excelで「2024-01」「01-05」「1/2」などの文字列を入力したとき、意図せず日付形式に自動変換されることがあります。特に コード・ID・先頭ゼロ付きの番号 を扱う場合や、ハイフン区切りのテキスト入力が必要な場合は困る現象です。 この記事では、「Exce... -

Excel 文字列分割 方法:パラメータ文字列を列に分割する実務テクニック
システムログや設定ファイルなどでは、key=value のようなパラメータ形式のデータがよく登場します。これを Excel 上で扱いやすくするためには、「=(イコール)」を基準に文字列を分割して キー と 値 に分ける作業が欠かせません。 本記事では、Excel の... -

VLOOKUP XLOOKUP 違い|どっちを使うべき?メリット・デメリットを徹底解説【Excel】
Excelで検索・参照作業をする際に必ず登場するのがVLOOKUPとXLOOKUP。2020年以降、Microsoftは「VLOOKUPの後継」としてXLOOKUPを標準搭載し、実務ではXLOOKUPへの移行が主流になりつつあります。 しかし、 「もうVLOOKUP使わない方がいい?」 「XLOOKUPっ... -

Excel:URLが勝手にリンクにならない・青字にならない時の解決方法
Excel では通常、URLを入力すると自動的に青字のハイパーリンクに変換されます。しかし、ある日突然 勝手にリンクにならない/青字にならない/クリックできない というトラブルが発生することがあります。 本記事では、ExcelでURLがリンク化されない原因... -

Excel:散布図に近似曲線を追加して予測値を算出する方法
Excelで売上予測やトレンド分析を行う際、散布図に近似曲線(回帰曲線)を追加し、さらに予測値を算出できることをご存じでしょうか。 本記事では、初心者の方でもわかりやすいように、 散布図の作り方 近似曲線の追加方法 予測値(将来値)の求め方 回帰...