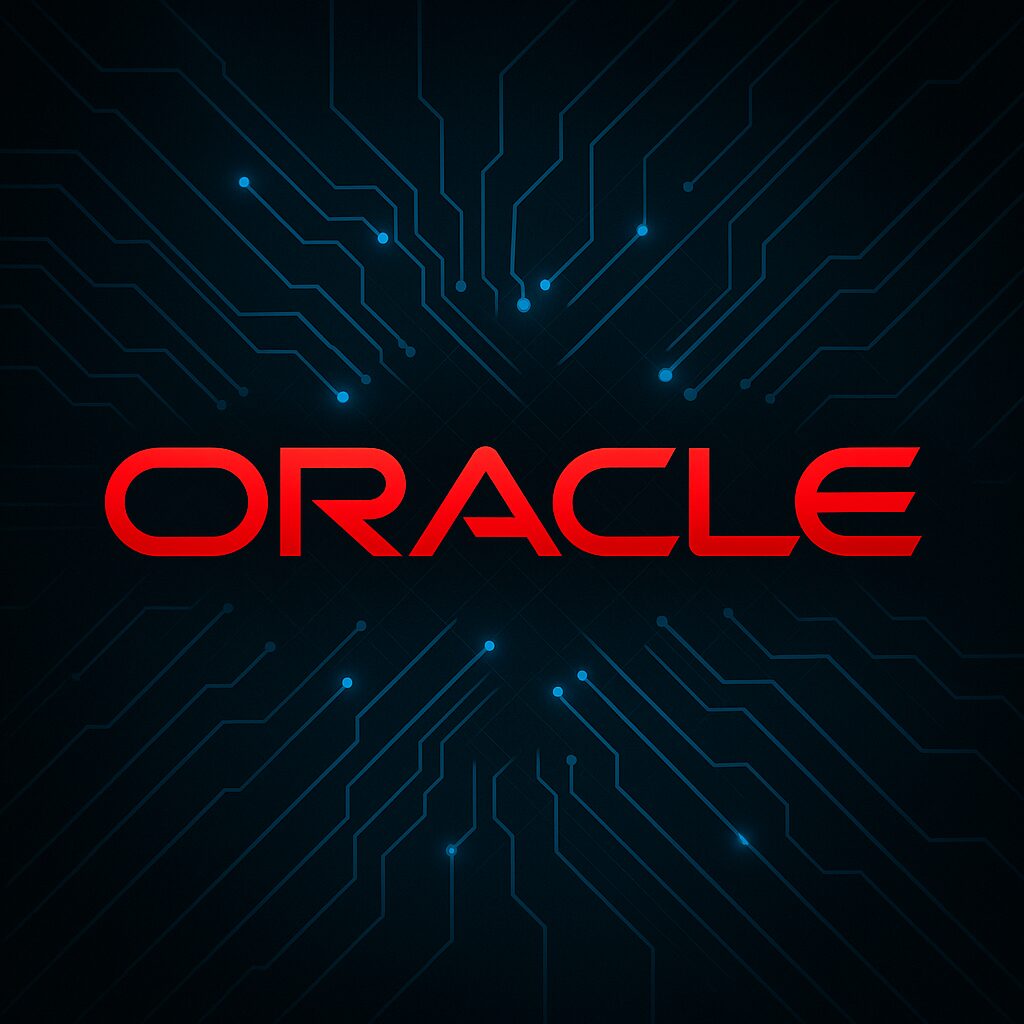Oracle– category –
-

ORA-02291 : 整合性制約違反(親キーがありません)の原因と対処法
Oracle Database を利用していると、INSERT や UPDATE 実行時に ORA-02291: 整合性制約違反(親キーがありません) というエラーに遭遇することがあります。 本記事では、 ORA-02291 の意味 よくある発生原因 実務で使える対処法 SQL 例を交えた確認手順 ... -

Oracle:ORA-29275|不完全なマルチバイト文字エラーの発生原因と対処法
Oracle Database を利用していると、文字コード関連の処理で突然次のようなエラーが発生することがあります。 [crayon-696f8786913d6753200674/] 本記事では、ORA-29275 エラーが発生する原因と、具体的な対処法・回避策をわかりやすく解説します。特に、U... -

ORA-04068 : パッケージの既存状態は廃棄されました の原因と対処方法
Oracle Database を利用したシステム運用やバッチ処理において、突然発生する ORA-04068 エラーに戸惑った経験はないでしょうか。 このエラーは一見すると致命的に見えますが、原因を正しく理解すれば、想定通りの挙動であるケースがほとんどです。 本記事... -

ORA-00936: 式がありません の原因とSQL修正例
Oracle Database を使用していると、SQL 実行時に次のようなエラーに遭遇することがあります。 ORA-00936: 式がありません 一見すると分かりにくいエラーですが、原因は SQL構文のごく基本的なミスであることがほとんどです。本記事では、ORA-00936 が発生... -

ORA-01555 : スナップショットが古すぎます の原因と対処法
Oracle Database を利用していると、長時間実行される SELECT 文や バッチ処理の途中で、次のようなエラーに遭遇することがあります。 [crayon-696f87869261d203850682/] 本記事では、ORA-01555(スナップショットが古すぎます) が発生する仕組みと原因、... -

ORA-01427 エラーの原因とは?単一行副問合せで複数行が返る理由と修正方法
Oracle を使った SQL 開発や運用の現場で、次のようなエラーに遭遇したことはないでしょうか。 [crayon-696f878692b7a042069270/] このエラーは 「1行だけ返るはずの副問合せ(サブクエリ)が、実際には複数行を返してしまった」 場合に発生します。SQL の... -

ORA-03137:TTCプロトコル内部エラーの原因と対処方法
Oracle Database を利用したアプリケーションやツールで、次のようなエラーに遭遇することがあります。 [crayon-696f8786930c9713718880/] 日本語環境では「ORA-03137: 不正な通信パケットを受信しました」と表示されることもあります。 このエラーは SQL... -

ORA-06550 : PL/SQL コンパイルエラーの原因と対処方法まとめ
Oracleで PL/SQL を実行・作成した際によく発生するエラー のひとつが ORA-06550 です。このエラーは単体で表示されることは少なく、PLS-xxxxx 系エラーとセットで出力されるのが特徴です。 本記事では、 ORA-06550 の意味 エラーメッセージの正しい読み方... -

ORA-08177 |can’t serialize access for this transaction:シリアライズエラーの原因と対処方法
Oracle でトランザクションを扱っていると、ORA-08177: can't serialize access for this transaction が突然発生することがあります。特に READ ONLY トランザクションモード(SERIALIZABLE) を使っていたり、UPDATE の競合が起きやすいバッチ処理では頻... -

ORA-01422 | Expected single row/完全フェッチがリクエストより多くの行を戻しました の意味と解決方法
Oracle PL/SQLで SELECT INTO を実行した際に、想定より多くの行が返ってしまうと発生するエラーが ORA-01422 です。特に「必ず1件しか返らないはず」というロジック前提で処理を書いた場合に多く発生します。 この記事では、ORA-01422の意味、原因、発生...