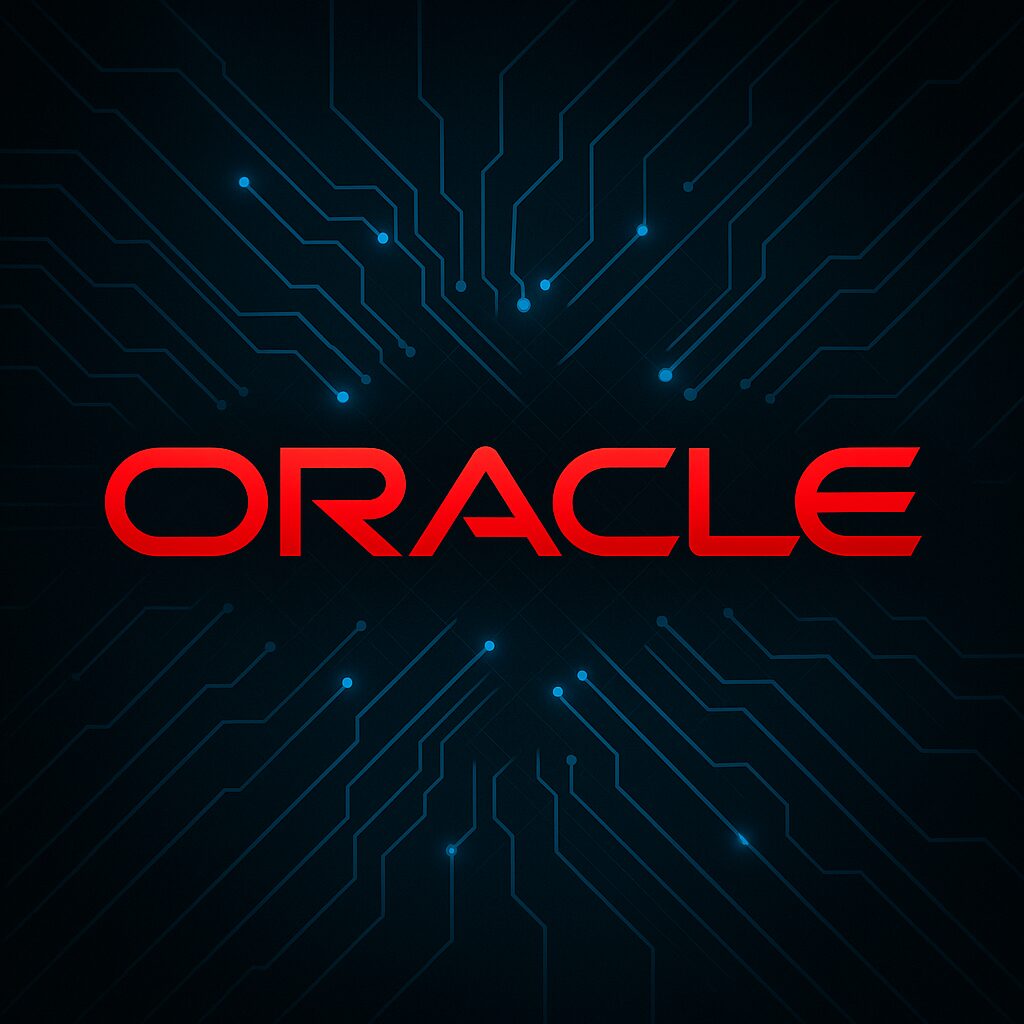Oracle– category –
-

ORA-01403 | データが1件も返らない時の典型原因と修正方法
Oracleデータベースでアプリケーション開発をしていると、時々遭遇するエラーが ORA-01403: no data found です。特にPL/SQLやSELECT INTO構文を使った処理でよく発生します。 この記事では、 ORA-01403が発生する状況 よくある原因 実務レベルでの修正方... -

ORA-01400 NULLを挿入できません|INSERT時のエラー原因と対応手順
OracleでINSERT文を実行した際、次のようなエラーが表示されることがあります。 [crayon-696f9e85c29b5586896980/] このエラーは、NOT NULL制約が設定されているカラムにNULL値を挿入しようとした場合に発生します。SQLを修正するだけではなく、アプリ側の... -

ORA-06512 が出たときの対処法|エラー行の見つけ方と典型的な原因まとめ
Oracleデータベースで PL/SQL を扱っていると、「ORA-06512」 がセットで表示されるエラーに遭遇することがあります。 このエラー自体は “直接の原因” ではありませんが、「どこでエラーが発生したか(行番号)」を示す重要なヒント になります。 本記事で... -

ora-00001|Oracleの一意制約(UNIQUE制約)違反の原因と対処方法
はじめに Oracleで最もよく見るエラーの1つが ORA-00001:一意制約(UNIQUE制約)違反。INSERT/UPDATE で突然エラーになり、原因が分かりづらいケースも多いです。 本記事では、UNIQUE制約でハマりやすいポイントと、ORA-00001の根本対策を実例付きで解説... -

【Oracle】ORA-12154エラーの原因と対処法まとめ:これで解決!
Oracleデータベースに接続しようとしたとき、「ORA-12154: TNS: 指定された接続識別子を解決できませんでした」 というエラーが出て焦ったことはありませんか? これはOracle初心者はもちろん、ベテランでも環境構築時によく遭遇する「あるある」エラーで... -

Oracle:ORA-03135「接続が失われました」の原因と対処方法|タイムアウト対策
Oracle DBへ接続しようとした際にORA-03135: connection lost contact(接続が失われました)というエラーが発生することがあります。 特にバッチ処理中や、長時間実行するSQL、アプリケーション側からの接続で発生しやすく、原因がネットワークにあるのか... -

ORA-12638:資格証明の取出しに失敗しました。が起きる時の対処方法
Oracle接続時に発生するエラー 「ORA-12638:資格証明の取出しに失敗しました。」 は、クライアント側の認証設定が原因で SQL*Plus やアプリケーション接続ができなくなるケースに多く見られます。特に Windows環境で Oracle Client を利用している場合や... -

【Oracle】ORA-01013:ユーザーによる処理中断エラーの原因と対処法まとめ
ORA-01013(user requested cancel of current operation) は、OracleでSQL実行中に処理が強制的に中断された場合に発生するエラーです。 エラーメッセージだけ見ると「ユーザーがキャンセルした」と書かれているため、本当にユーザー操作なのか?アプリ... -

【Oracle】ORA-03113:通信チャネルEOFエラーの原因と解決手順をわかりやすく解説
■ ORA-03113とは? ORA-03113: end-of-file on communication channel は、Oracle クライアントとサーバ間の通信が異常終了したとき に表示される代表的なエラーです。 平たく言うと、 「通信中にいきなり回線が切れた / Oracle が応答しなくなった」とい... -

ORA-12541の原因と対処法|「TNS: リスナーがありません。」エラーを最速で解決する方法
Oracle接続時に突然出る ORA-12541: TNS: リスナーがありません。現場でも頻出するエラーの1つで、接続テストが通らない・アプリがDBに繋がらないなどのトラブルを引き起こします。 この記事では、最速で復旧するためのチェック手順 → 原因の深掘り → 正し...