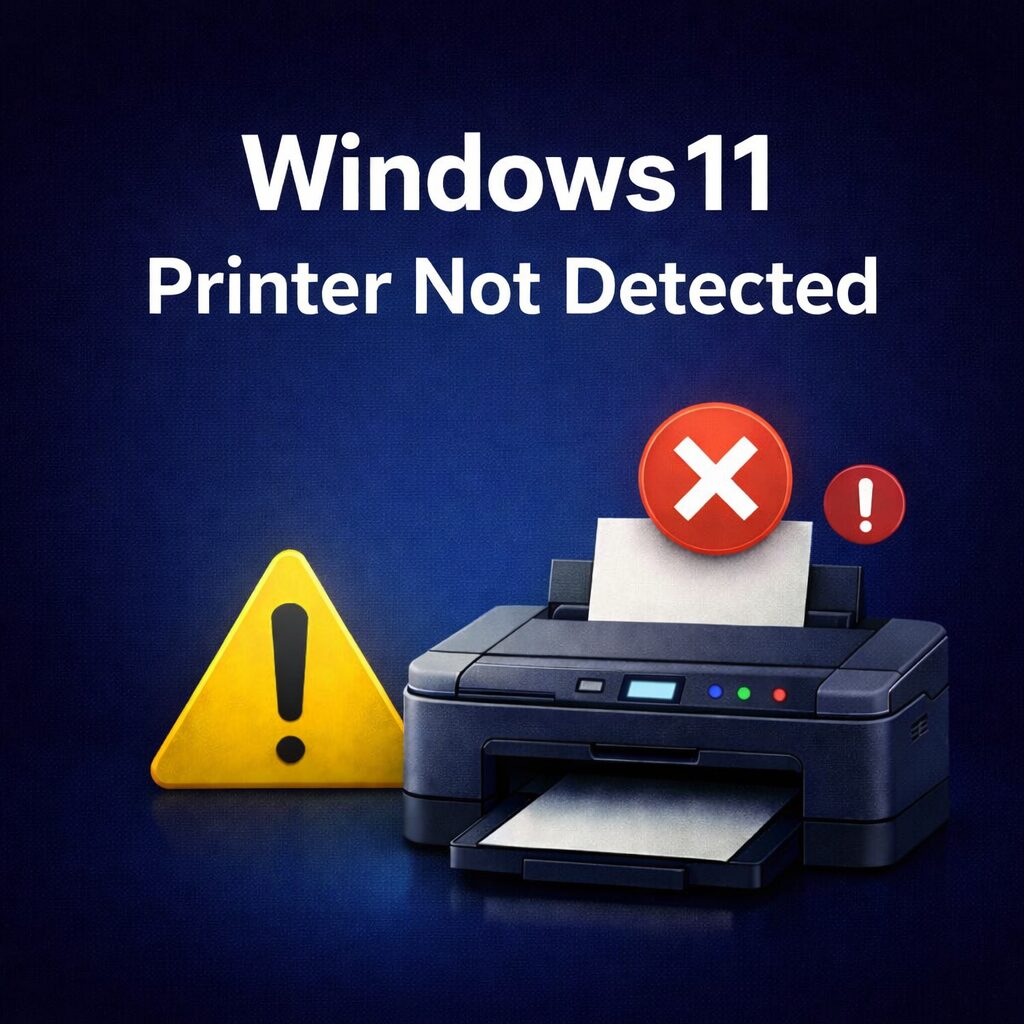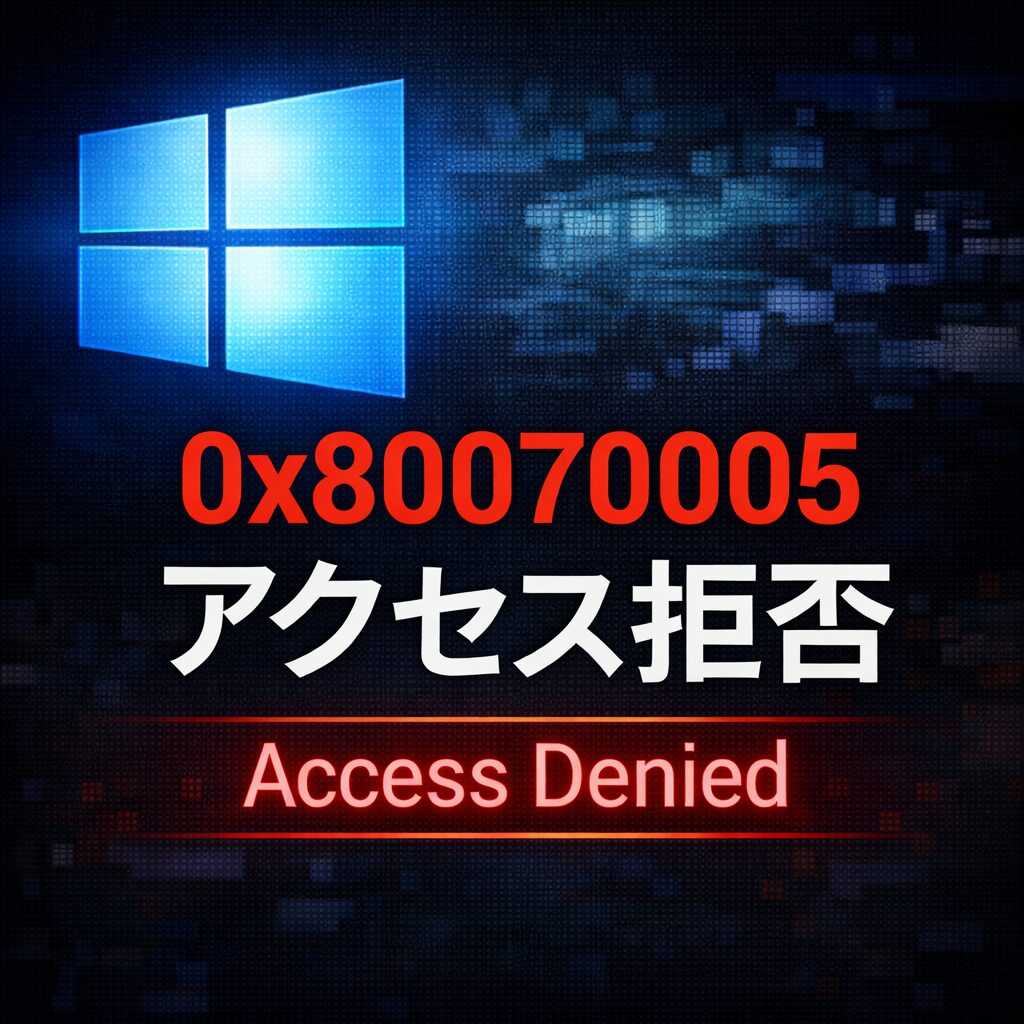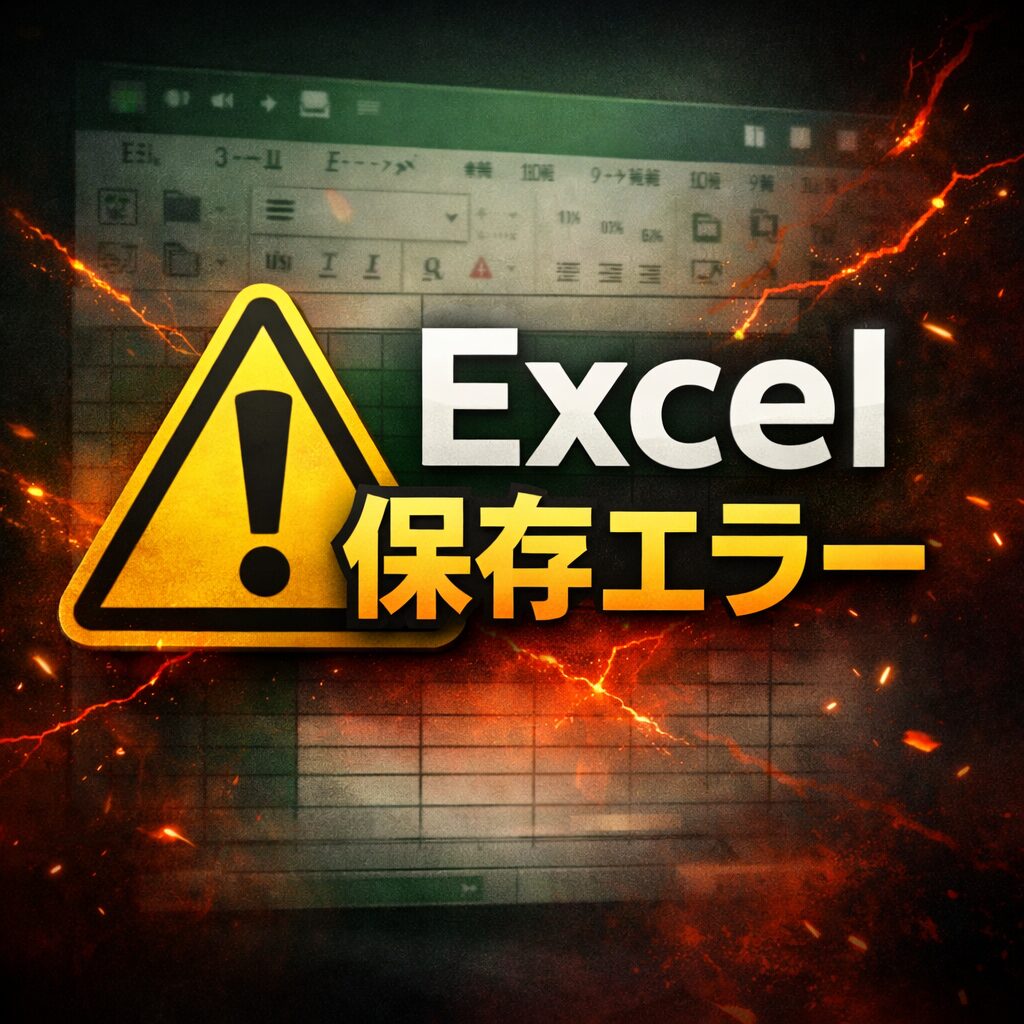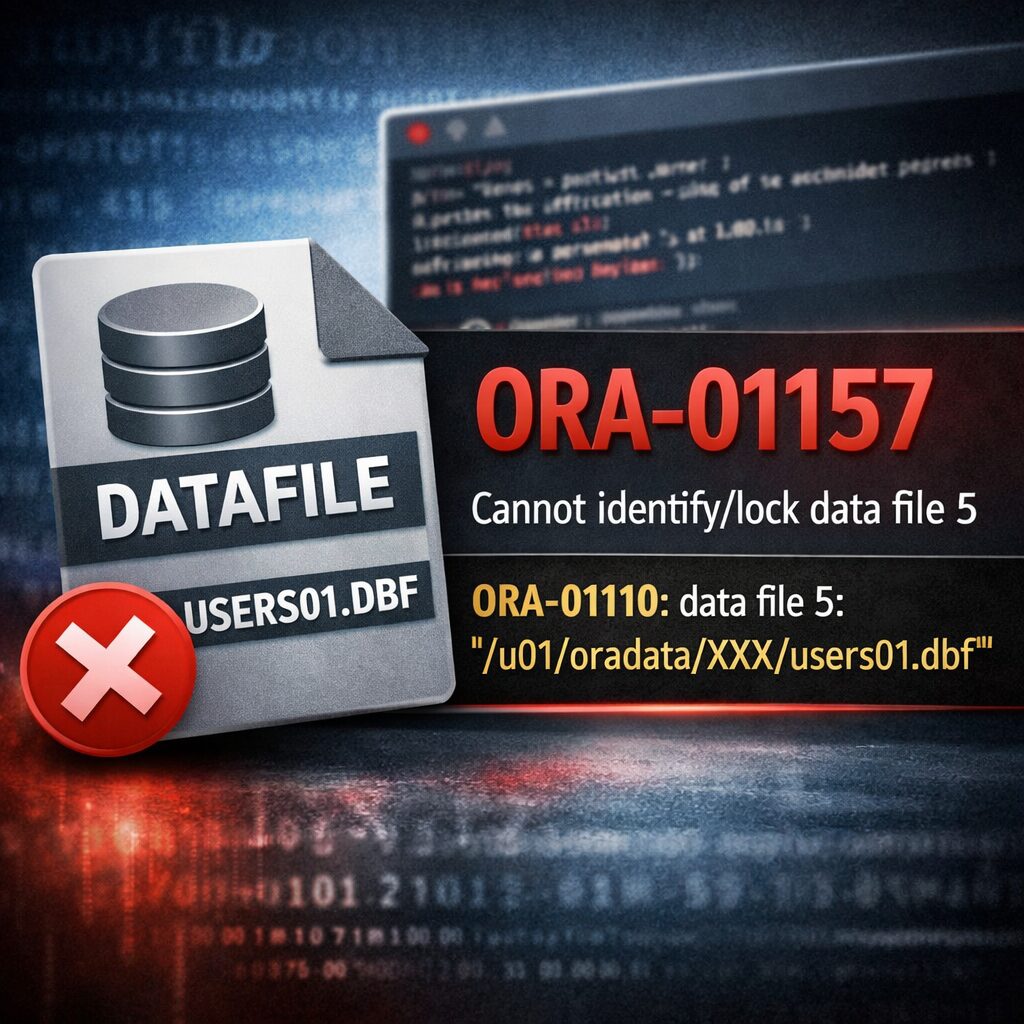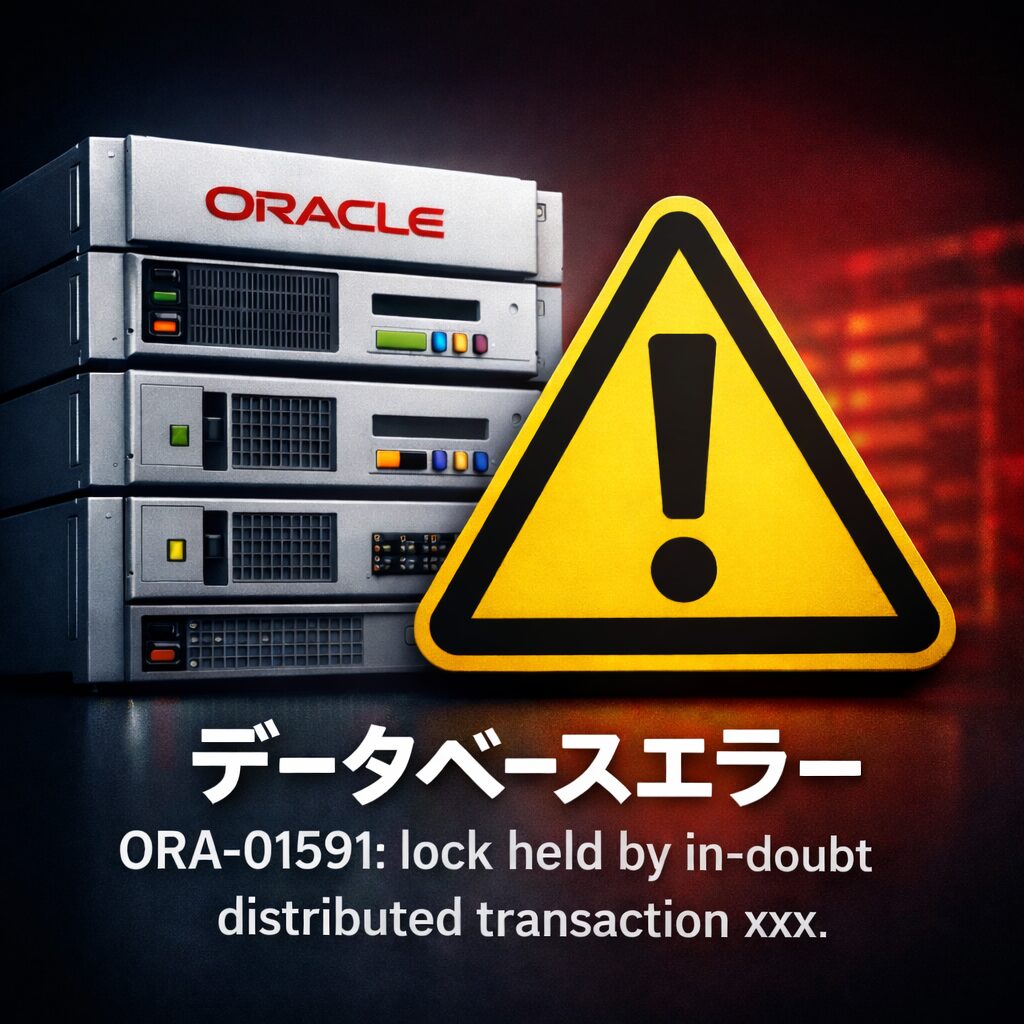トラブル対応– category –
トラブル対応に関する記事です
-

ORA-01461 : LONG列にバインドできません の原因と対処法
Oracle Database を利用したアプリケーション開発や運用において、INSERT や UPDATE を実行した際に「ORA-01461: LONG列にバインドできません」というエラーが発生することがあります。このエラーは一見分かりにくいものの、Oracleのデータ型仕様を正しく... -

Windows11 : 0x800f081f 更新プログラムを適用できない理由
Windows Update を実行した際に エラーコード「0x800f081f」 が表示され、更新プログラムを適用できないケースがあります。このエラーは一時的な通信不良ではなく、Windows の内部コンポーネントや更新ソースに問題がある場合に発生することが多く、放置す... -

How to Fix “Printer Not Detected” on Windows 11
If you’re using Windows 11 and suddenly your printer isn’t being recognized — or if you can’t add a new printer — this guide will help you diagnose and fix the problem step-by-step. Symptoms You Might See You may experience one or more o... -

Windows11 : 0x80070005 アクセスが拒否されました|原因と対処法
Windows を操作していると、更新やアプリの実行、Office のライセンス認証などの場面で「0x80070005 アクセスが拒否されました」というエラーが表示されることがあります。 このエラーは一見すると原因が分かりづらく、再起動や再試行を繰り返しても解決し... -

ORA-00932 : データ型が一致しません の原因と対処法
Oracle Database を利用した SQL 開発や運用の現場では、構文自体に誤りがないにもかかわらず実行時にエラーが発生するケースがあります。その代表例の一つが 「ORA-00932 : データ型が一致しません」です。 このエラーは、SQL 文の中で異なるデータ型が不... -

Excel:保存できない/名前を付けて保存が出る原因と対策
Excelを使用していると、 ・「上書き保存したはずなのに保存できない」 ・「保存ボタンを押すと毎回『名前を付けて保存』が表示される」 といった現象に遭遇することがあります。この問題は、Excelの設定だけでなく、ファイルの保存場所や権限、他アプリと... -

Windows11 無線LAN接続トラブルの原因一覧と対処方法
Windows11を利用していて「突然Wi-Fiに繋がらなくなった」「無線LANが表示されない」「接続済みなのに通信できない」といったトラブルに遭遇するケースは少なくありません。無線LANの問題は、設定・ドライバ・Windowsの機能・ネットワーク機器など、複数の... -

ORA-01157 : データファイルを識別できません|発生時の確認ポイント
Oracle Database を運用していると、ある日突然 ORA-01157 : データファイルを識別できません というエラーに遭遇することがあります。このエラーは、単なる SQL 実行エラーではなく、データベースの物理ファイルに関する重大な問題 を示しています。対応... -

Zoomのカメラが映らない原因と今すぐできる対処方法
オンライン会議や打ち合わせで広く利用されている Zoom ですが、「急にカメラが映らなくなった」「自分だけ映像が真っ暗になる」といったトラブルは珍しくありません。カメラが使えない状態では、会議への参加自体が難しくなる場合もあり、早急な対処が求... -

ORA-01591:インダウト分散トランザクションがロックを保持する原因と対処法
Oracle Database を運用している環境において、ある日突然 DML や DDL が待たされ、調査を進めると「ORA-01591:インダウト分散トランザクション xxx がロックを保持しています。」というエラーに遭遇することがあります。 このエラーは、通常のロック競合...