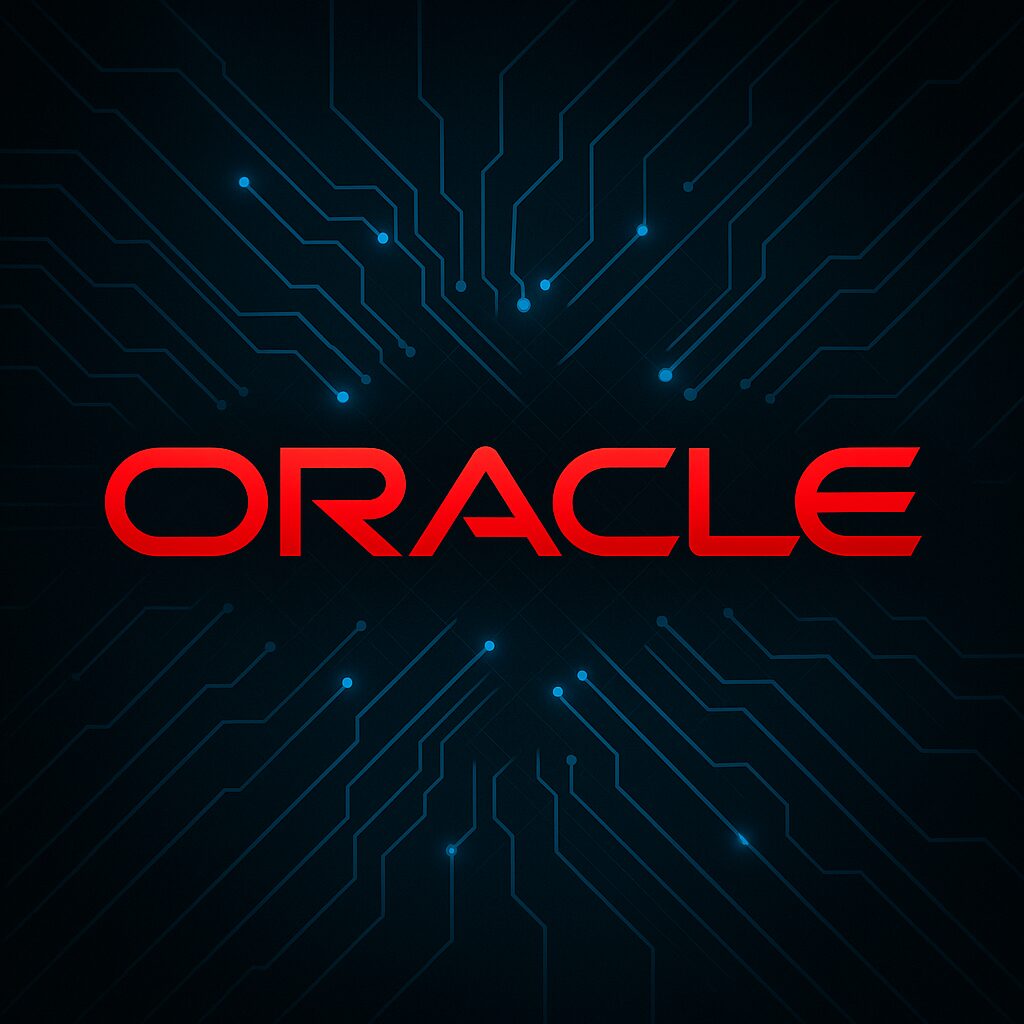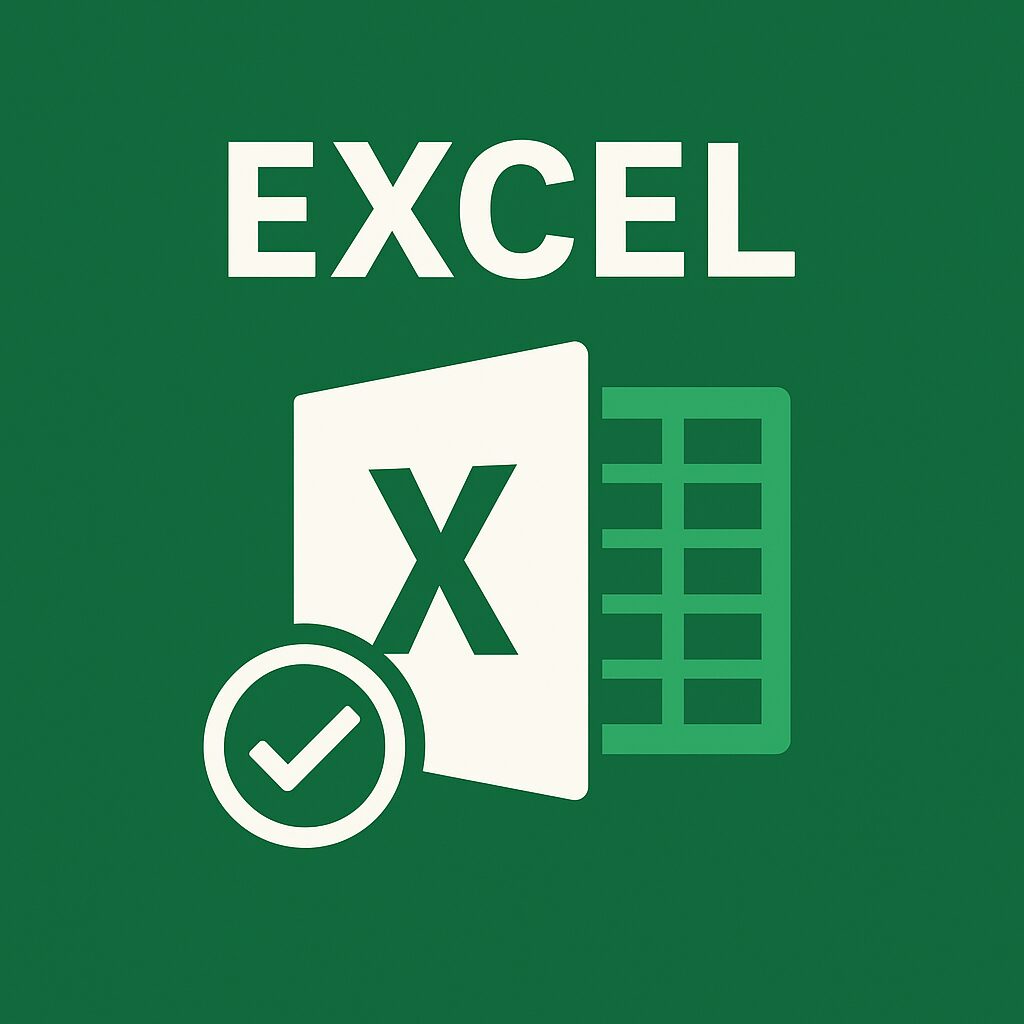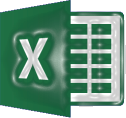管理者– Author –

「駑馬十駕」を信念に IT系情報を中心に調べた事をコツコツ綴っています。
-

HULFTで日付付きファイルを配信元ファイル名のまま受信する方法
HULFTを使ったファイル連携では、バッチ処理などで日付が付与されたファイル名を扱うケースが多くあります。例えば、送信側で以下のように日付が付与されたファイルを生成する場合です。 sales_20250911.csvsales_20250912.csv 受信側でもこのファイル名を... -

Oracleユーザー作成時にORA-00959エラー発生!指定された表領域が存在しない場合の対処法
はじめに Oracle Databaseでユーザーを作成する際に、以下のようなエラーが発生することがあります。 ORA-00959: tablespace 'USERS' does not exist このエラーは、指定した表領域(tablespace)が存在しない場合に発生します。本記事では、原因の解説と... -

ChatGPTにExcelマクロを書かせてCSVを自動処理|初心者でもできるフィルタリング自動化
はじめに 業務でCSVデータを扱う機会は多いですが、毎回手作業でフィルタリングするのは大変です。そんなときに便利なのが Excelマクロ(VBA)による自動処理。 しかも今は、ChatGPTに「CSVを読み込んでフィルタリングするマクロを書いて」と依頼するだけ... -

👉 ChatGPTでできるExcel自動化の基本4ステップ|列A+Bを合計して列Cに表示する方法
毎日のExcel作業で「同じ計算を繰り返すのが面倒…」と感じていませんか? 実はChatGPTを使えば、数行の依頼だけでExcelマクロを自動生成でき、作業を一気に効率化できます。 この記事では、列Aと列Bを合計して列Cに表示するシンプルなマクロをChatGPTに作... -

CSVファイルの 「BOMあり」、「BOMなし」とは?
はじめに CSVファイルを扱っていると、「BOMあり」「BOMなし」という言葉を目にすることがあります。特にExcelで開いたときに文字化けしてしまった経験がある方は、この違いが大きな意味を持つことを知っておくと便利です。この記事では、BOMの基礎から、E... -

Excel:半角・全角文字のチェック方法
Excelを使用して文字列の中に半角文字が含まれてるかどうかを確認する方法です。 半角文字の有無を確認するにはLEN関数とLENB関数の結果を比較することで文字列の中に半角文字が含まれてるかどうかを確認出来ます。 LEN関数とLENB関数を使用して半角文字の... -

Oracle:COALESCE関数の使い方
oracleの独自関数のCOALESCE(コアレス)関数の用途についてメモしておきます。 COALESCE関数とは COALESCE関数は引数のリストから最初のNULL以外の値を返却するOracle独自関数となります。 NVL2関数との違いは必ずしも引数へ指定するデータ型を全て合わせ... -

Oracle:NVL関数とNVL2関数の違い
oracleの独自関数としてNVL関数やNVL2関数があります。 知ってると結構便利な関数なので、この2つの関数の違いについて整理しておきます。 NVL関数とは NVL関数は第1引数がNULLなら第2引数の値(代替値)を返します。 もし第1引数の結果がNULLでなけれ... -

INSERT文を指定回数分ループして実行する方法
性能試験などであるテーブルに大量データの作成が必要になった場合にINSERT文をループで処理できれば便利!という事で、SQLとロジックを組み合わせたストアドプロシージャでのサンプルプログラムとなります。 ストアドプロシージャ DECLARE -- 変数の宣言 ... -

Excel:文字列で入力済の値を数値形式へまとめて変換する方法
Excelで文字列として入力済の値をまとめて数値形式へ変換する方法です。 以下の様にA1~A3セルへは文字列として入力しており、A4セルで集計してますが文字列なので0表示されてしまっています。 このA1~A3セルの文字列を数値形式に変換してみます。 数値...