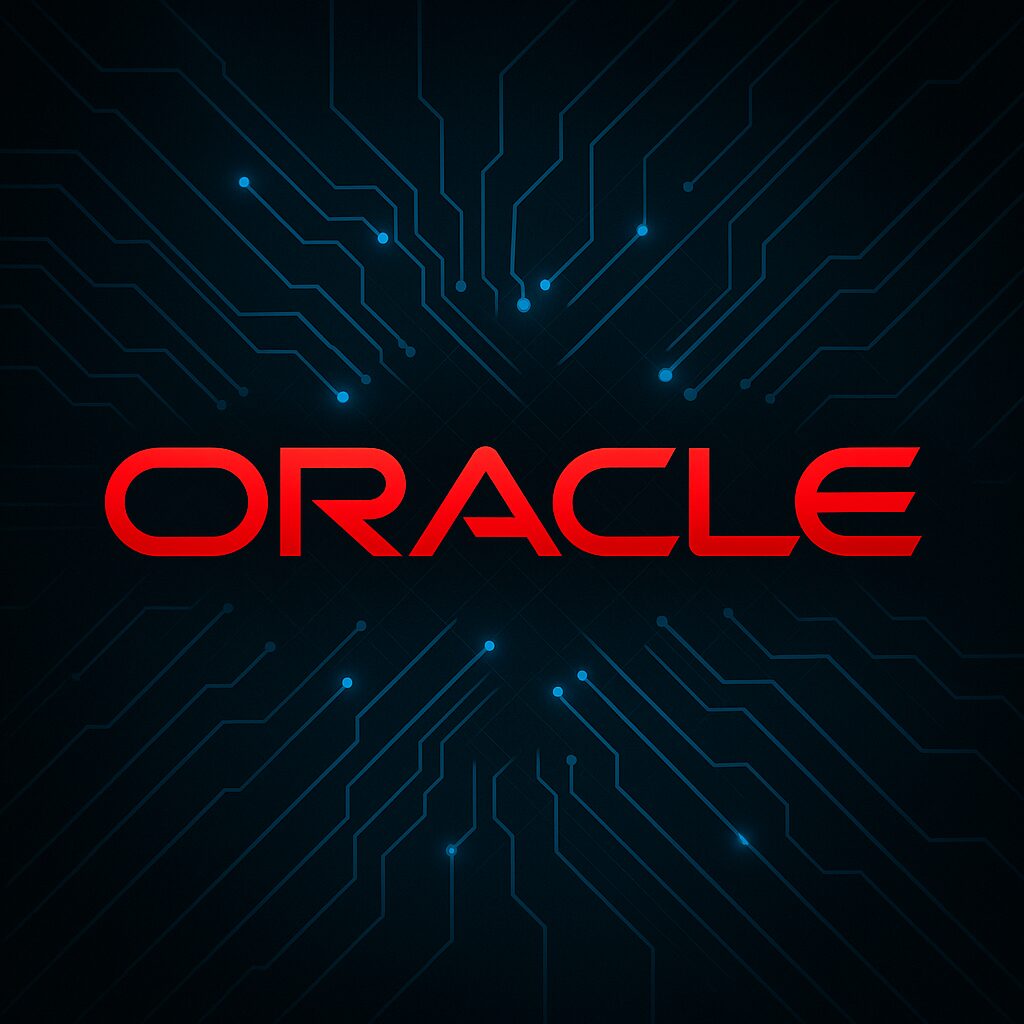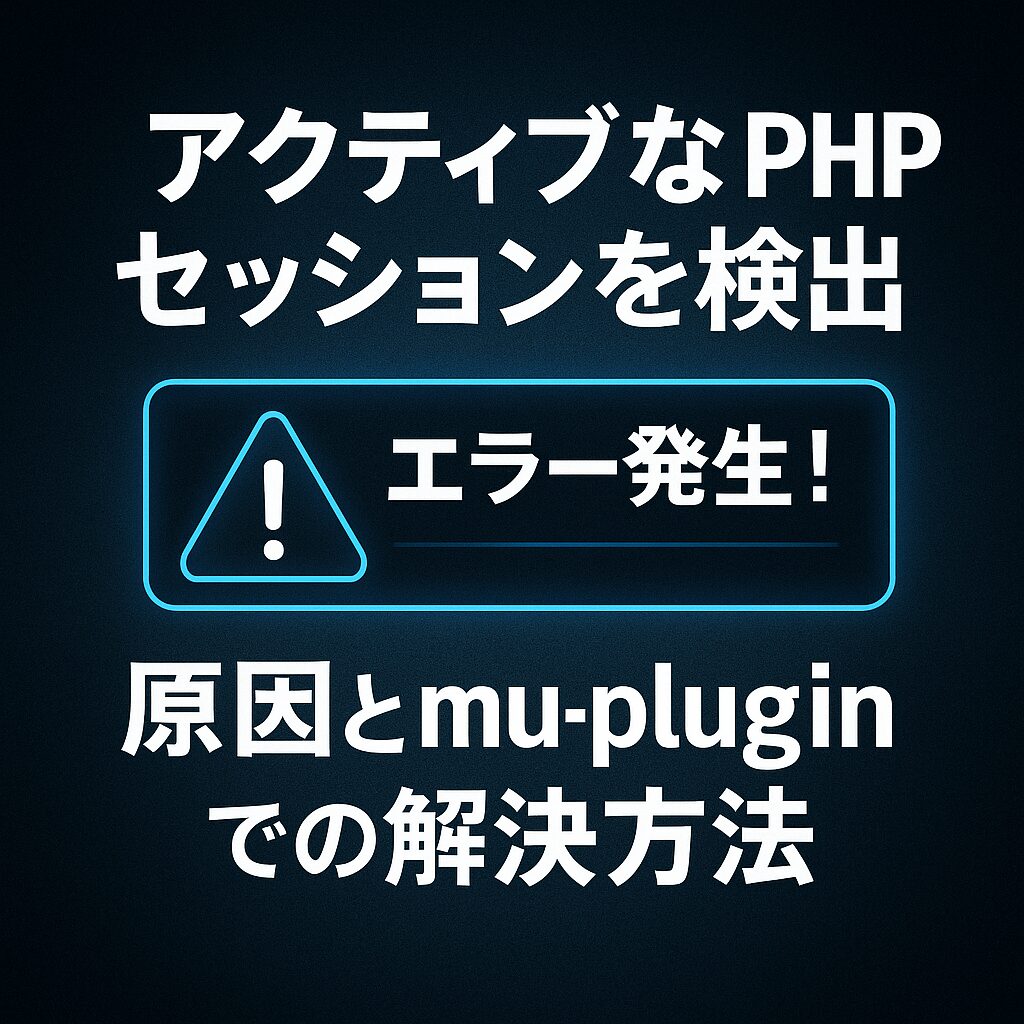管理者– Author –

「駑馬十駕」を信念に IT系情報を中心に調べた事をコツコツ綴っています。
-

Mapの操作がここまで楽になる!Java 8のcomputeIfAbsent/merge徹底活用術
はじめに:Map操作、まだ「containsKey」で書いていませんか? JavaでMapを使うとき、以下のようなコードを書いた経験はありませんか? [crayon-69771c919d96c723805735/] Java 8以前ではこれが一般的でした。しかしJava 8では、computeIfAbsentやmergeを... -

バッチ処理での変数トラブル解消!EnableDelayedExpansionでリアルタイム展開を実現する方法
Windowsのバッチファイル(.bat/.cmd)で FOR や IF を使った処理を記述していると、「変数が更新されない」「値がループ中で変わらない」といった問題に直面することはありませんか? その原因は、変数が「実行前に展開される」ためです。この問題を解消... -

Excel vs Googleスプレッドシート:機能・関数・用途の違いをわかりやすく解説
「ExcelとGoogleスプレッドシート、どっちを使えばいいの?」「関数の違いが知りたい」「チームで作業するならどちらが便利?」このような疑問を持つ人は多いです。 Excelは企業でも広く使われる表計算ソフトの定番であり、一方でGoogleスプレッドシートは... -

Oracle「ORA-02292:整合性制約が違反しています」の原因と解決法
データ削除(DELETE)や更新(UPDATE)を行った際に、次のようなエラーが発生したことはありませんか? ORA-02292: 整合性制約 (制約名) が違反されています - 子レコードが見つかりました。 このエラーは、「削除しようとしたデータが別のテーブルから参... -

Windows 11:省電力モード・高パフォーマンス設定の切り替え方法
「バッテリーを長持ちさせたい」「ゲームや動画編集時にパフォーマンスを最大化したい」──そんなときに活用できるのが、Windows 11の「電源モード」や「電源プラン」の切り替え機能です。 この記事では、「設定アプリ」から簡単に切り替える方法と、より細... -

SQL:MERGE文でINSERTとUPDATEを一度に行う効率的な方法
MERGE文とは? SQLのMERGE文は、対象テーブルにデータが存在する場合はUPDATE、存在しない場合はINSERTを1回の処理でまとめて行える便利な構文です。従来は「UPDATE → 該当しなければINSERT」といった2回の処理が必要でしたが、MERGEを使うことで1回のSQL... -

if文から卒業!Java 8のPredicateで条件分岐をスマートに書く方法
Javaで複雑な条件分岐が増えてくると、if文がネストして読みにくくなる…という悩みを抱えたことはありませんか?Java 8で追加されたPredicateインターフェースを使えば、条件式をオブジェクトとして扱えるため、よりスマートで再利用可能な形にできます。 ... -

WordPressで「アクティブなPHPセッションを検出」エラー発生時の原因とmu-pluginでの解決方法
WordPress のサイトヘルス(Site Health)で、次のような警告が表示されて困ったことはありませんか? 🧩 発生した警告内容 「アクティブな PHP セッションが検出されましたWordPress のパフォーマンスを改善するために、HTTP リクエスト前にセッションを... -

Windows 11:cmdからシステム情報を一括取得する便利コマンド集
「自分のWindows 11のスペックを知りたい」「トラブル発生時にシステム情報をまとめて取得したい」──そんなときに役立つのが、コマンドプロンプト(cmd)で使えるシステム情報取得コマンドです。 この記事では、Windows 11でシステム情報を一括確認できる... -

WordPress サイトヘルスの「REST API でエラーが発生しました(cURL error 28)」の原因と対処方法
WordPress のサイトヘルス診断で、以下のようなエラーが表示されたことはありませんか? REST API のテスト時にエラーが発生しました:(http_request_failed) cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received このエラ...