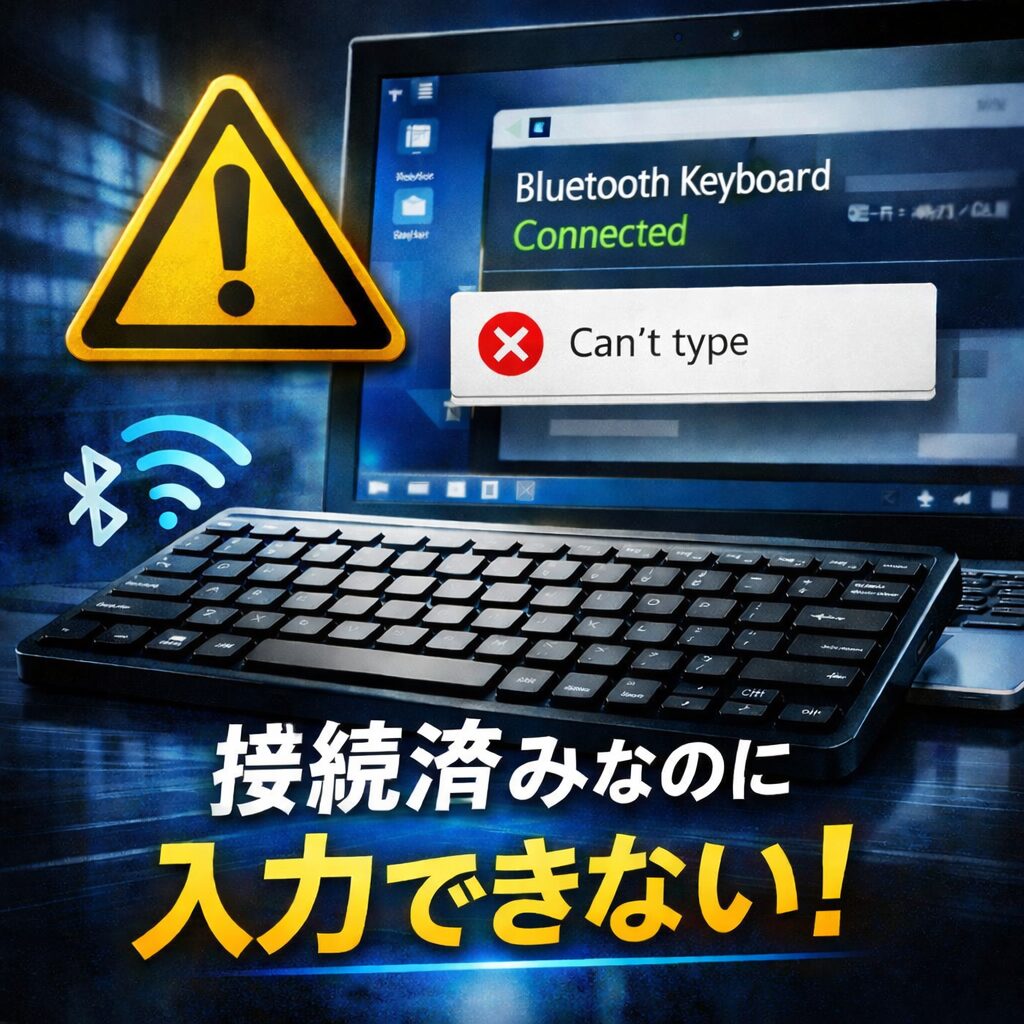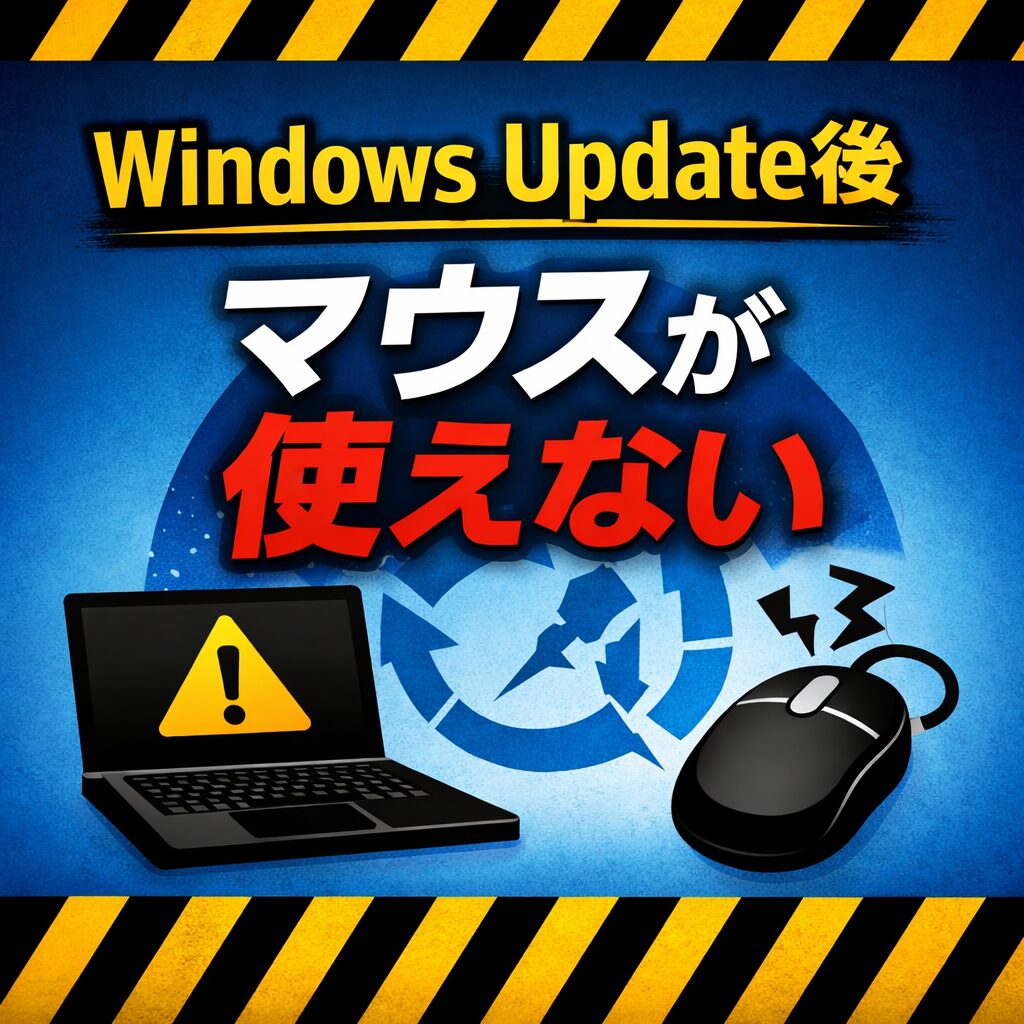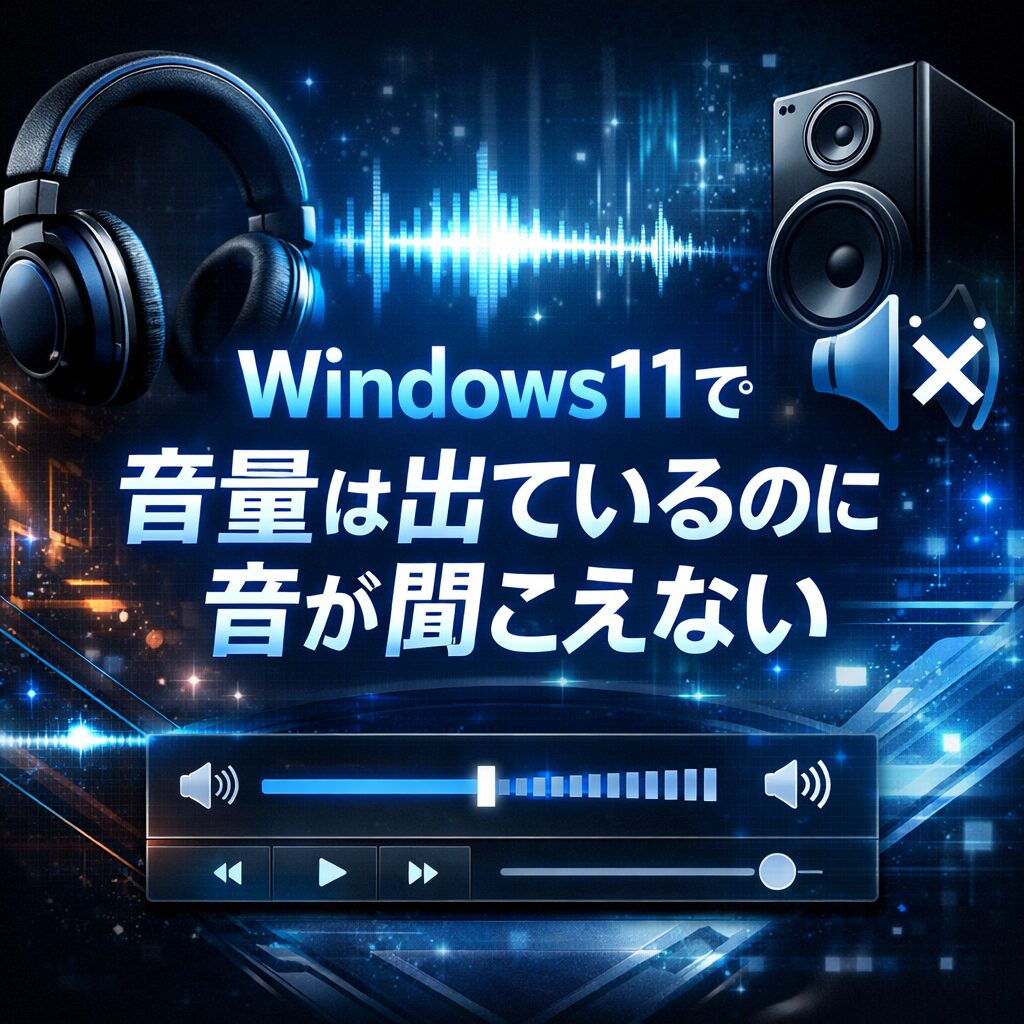ブログ– category –
ブログ投稿用のカテゴリ
-

PowerShellで不要なソフトを一括削除する手順【業務PC管理】
業務用PCでは、意図しないソフトや不要なアプリケーションがインストールされたままになっているケースが少なくありません。これらを放置すると、セキュリティリスクの増加、ディスク容量の圧迫、動作パフォーマンスの低下など、業務に直接影響する問題が... -

Windows Update後に音が出なくなった時の原因と対処法【Windows11】
Windows Update を実行した直後から、スピーカーやヘッドホンから突然音が出なくなったというトラブルは、Windows11 では珍しくありません。更新直前までは問題なく音が出ていたにもかかわらず、再起動後に無音になるため、故障や重大な不具合を疑ってしま... -

Bluetoothキーボードが接続されているのに入力できない理由
Bluetoothキーボードが「接続済み」と表示されているにもかかわらず、文字入力が一切できない、または一部のキーだけ反応しないというトラブルは、Windows 11 を中心に非常によく報告されています。この問題はキーボード本体の故障だけが原因ではなく、OS... -

Excelで変更を保存できない時に確認すべきポイント
Excelを使用して作業を行っている際に、セルの内容を変更したにもかかわらず「保存できない」「上書きできない」「変更が反映されない」といったトラブルが発生することがあります。業務中に突然この状態になると、作業が中断されるだけでなく、最悪の場合... -

Windowsでアカウントが乗っ取られた可能性がある時の確認方法
Windowsを使用している中で、「身に覚えのない操作履歴がある」「設定が勝手に変わっている」「警告メールが届いた」など、不正アクセスを疑う状況に気づくことがあります。このような場合、焦って操作を進めてしまうと、かえって被害を拡大させる恐れがあ... -

Windows11でマイクが突然使えなくなった時の対処手順
Windows11を使用していて、これまで問題なく使えていたマイクが突然認識されなくなったり、音声が入力されなくなったりすることがあります。オンライン会議や通話、録音作業の直前に発生すると非常に困るトラブルの一つです。 本記事では、Windows11でマイ... -

Windows Update後にマウスが使えなくなった時の対処手順【Windows11】
Windows 11 では、Windows Update 後に突然マウスが反応しなくなる、カーソルが動かない、クリックできないといったトラブルが発生することがあります。特に、アップデート直後に再起動したあとから使えなくなるケースは非常に多く、ハードウェア故障と誤... -

Microsoftアカウントに不正ログインされた時の対処法
Microsoftアカウントに身に覚えのないログイン履歴が表示されると、強い不安を感じる方が多いと思います。Outlook、OneDrive、Microsoft 365、Windows へのサインインなど、Microsoftアカウントは多くのサービスと連携しているため、不正ログインを放置す... -

Windows11で音量は出ているのに音が聞こえない原因
Windows11を使用していると、音量メーターは動いているのに実際には音が聞こえないというトラブルが発生することがあります。スピーカーの音量もミュートではなく、再生中のアプリでも音量が出ている表示なのに無音のまま、という状態です。 この症状はハ... -

Gmail でメールが送信できない・受信できない原因と対処法
Gmail を使用している際に、メールが送信できない、または受信できないといったトラブルが発生することがあります。仕事や重要な連絡で Gmail を利用している場合、この問題は大きな支障となります。 本記事では、Gmail でメールが送信できない・受信でき...